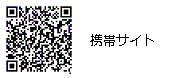一つのことにとらわれずに
第44回(令和6年度)
全国高校生読書体験記コンクール入賞
小林優芽さん(新潟県立三条高等学校)
(取り上げた書名:『アルジャーノンに花束を』/著者名:ダニエル・キイス/出版社名:早川書房)
初めて本書を読んだとき、衝撃をうけた。文章のほとんどが平仮名で誤字脱字がとても多かったからだ。
ダニエル・キイス作の『アルジャーノンに花束を』は一九五〇年代のアメリカニューヨークを舞台に知的障害のあるチャーリイ・ゴードンが、ある手術を受けて高い知能をもつことになる物語だ。
私が本書と出会ったのは、あるテレビドラマの主題歌となっていた『アルジャーノン』という曲がきっかけだった。あるとき、この曲にはモチーフとなった小説があるということを知った。それが『アルジャーノンに花束を』だった。
冒頭で述べた誤字脱字の多さは主人公のチャーリイが知的障害であることが原因である。本書は彼が受けた手術の研究の一環として彼が記した経過報告という形で物語が描かれている。そのため物語の初頭は誤字脱字がとても多く、子どもが書いたような文章になっている。そして物語が進むにつれて誤字脱字がなくなり、普通の小説のような文章になっていく。私が驚いたのは、その自然な文章の変わり様だ。徐々に大人な文章に変わっていくのに、その変化が自然すぎて意識しないと分からない。この小説は英語で書かれ、アメリカで出版されて日本語に翻訳されている。日本語に訳す上で自然に文章の変化を表現するのはとても難しく、その技量を素晴らしいと感じた。
私がこの本を読んで感じたことは二つある。
一つ目は完璧な悪人などいないということだ。チャーリイにはジョウとフランツとギンピイという同僚がいた。チャーリイはジョウとフランツにいじめられていた。ギンピイはチャーリイをいつも庇っていたが、のちに職場で悪事を働いていて、知らぬ間にチャーリイ自身も加担させられていたことが発覚する。チャーリイは過ちを正そうとしたが、仕事をクビになってしまう。
これだけ聞くと彼らは悪人のように思えるが、チャーリイの知能が退行してまたパン屋で働くことになったとき、新人にいじめられていると、ギンピイ、ジョウ、フランツは彼を庇っていた。
私はこの場面がとても印象的で、彼らの言動は彼らが悪いことをしたからといって、それだけで一概に「悪い人」と決めつけられるわけではない人間の複雑さが表されていると感じた。私は誰かの負の面を見たとき、その一場面だけで相手を「悪い人」だと感じてしまうことが過去にあった。しかし、負の面はその人の一部分でしかなく、私が知らないだけであって、その人にも良い一面があったりするかもしれない。一つの印象だけで人を判断せず、たとえ相手が負の面を持っていたとしても、その人の良い一面を探していきたいと思った。
二つ目は本を読むとき私たちはしばしば主人公目線になりがちだということだ。私の読んだ早川書房の『アルジャーノンに花束を[新版]』には作者が書いた「日本語版文庫への序文」が載っていて、「世界じゅうの数多の読者から老若を問わず一様に、チャーリイ・ゴードンを自分の身におきかえて見たという手紙をもらった」という言葉がある。私も本書を読み進めるうちにチャーリイを自分に重ねて読んでいることに気がついた。そこでチャーリイの同僚の立場になってもう一度読んでみた。すると、チャーリイの立場のときは彼をクビにしてほしいと考える同僚たちは悪者と捉え、チャーリイに同情していたが、同僚の立場で読んだときは彼らの気持ちに共感できる自分がいた。周りの誰かが急にかしこくなったら気持ち悪いと感じるのは当然だと思った。彼らの感性は私と何ら変わりがない。その事実にとても驚いた。無条件に主人公の味方になるのではなく、他の立場から見たものや感じたことも大切にしていきたい。
私の兄のアルバイト先では多くのネパール人が働いている。彼らはやらなくても良いところまで仕事をして、回転率が悪くなっているようだ。しかし、実はネパールにはコミュニティを大切にするという文化がある。そのためネパール人同士で協力し合って仕事をすることで、その内の誰かの仕事が疎かになっていることが起きているのかもしれない。ネパールの文化を知る前と後では彼らの印象はガラリと変わる。
この世界にはいろいろな人がいる。ひとりひとり立場や性格は異なる。チャーリイとその同僚たちはひとつの角度からだけでなく、多方面から捉えることでそれまで気づかなかったことに出逢えると教えてくれた。これからは私も相手の立場になって相手のことをもっと知る努力をしていきたい。その努力が自分とは違う人たちと共生するという「多様性」につながっていくと私は思う。