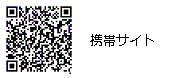人間不信革命
第44回(令和6年度)
全国高校生読書体験記コンクール入選
大髙志緒理さん(私立新潟清心女子高等学校)
(取り上げた書名:『六人の嘘つきな大学生』/著者名:浅倉秋成/出版社名:KADOKAWA)
他人から「空気を読め」だの「察しろ」と言われたことがある人はいるだろうか。これは当時小学二年生だった私にクラスメイトが投げ掛けた言葉である。言われた当初は、その場の雰囲気なんて目で見えない、皆の心の中がガラス張りで透けて見えるわけでもないのにと理不尽に思った。だが少し経って、クラスという小さな社会が出来上がった頃には、当たり前のようにその人の気分や立場に合った対応をするようになった。あの一言は些細だったが、確かに私の分岐点に違いない。思えばこの頃は本当に人の心を見抜いているつもりだったのだろうが、時が経つにつれそれがまやかしであることに気付いてしまう。
作中でこのような場面がある。会社の採用担当になってしまった衣織が、元人事部の鴻上に「相手の本質を一瞬で見抜くテクニック」を聞いたのだ。
「相手の本質を見抜くなんてね、保証しますけど、絶対に、百パーセント、不可能です。」これが鴻上の結論であり、私の短い人生の内の問いに対する結論でもあった。
私がこの本を読んでから衝撃を受けたのは緊迫した場面のところどころに挟まれる、登場人物へのインタビューだ。インタビューの内容は登場人物への印象を先刻までとは一転させ、読んでいた私は勝手に裏切られた気分になった。しかしよく考えてみてほしい。果たしてインタビューで語られた事が登場人物の全てなのか、ひいては就職試験の時に見せた姿が本当の性格なのか。それらは全部、断片的な情報でしかない。にも関わらず私は無意識にその断片的な情報で登場人物の全てを見抜いたように、評価を変えた。何度も。それがこの小説の醍醐味ではあるのだが、自分が無意識のうちに勝手に人に期待して失望するような考え方をしていたことに少なからず落胆してしまったのだ。
そんな私の心の翳りを晴らしてくれたのは、この作品の第一の主人公・波多野祥吾だ。前編にあたる就職試験編は彼の視点で進み、読者である私は感情移入しながら読み進めていた。前編ラストの結末はあまりにもやるせなくて、私も五人から裏切られたような気分になったのを覚えている。しかし彼はわずか半年で立ち直ったのだ。
「彼らが悪人ではないことを、僕はどうしようもなく知っていた。彼らが優秀で、素晴らしい人間であることを、愛すべき仲間であることを十分に理解できていた。」
私はこの言葉で、いかに自分が大切なことを忘れていたのか痛感した。皆の輝やかんばかりの活躍と魅力を彼と一緒に見てきたではないか。私は自分が見聞きしたこと、感じたことの全てを、信じてあげていなかったのだ。
人の本質は見抜けない、空気を読めと言われて必ず正解に辿り着けるわけでもない、やっぱり無意識に人に失望してしまう。これらはきっと、集団生活をする人間にとってごく普通の反応なのだろう。人と関わる以上、やはり褒められないような一面が垣間見えてしまうこともある。だがそのイメージだけに引っ張られてはいけない。その人と関わって、嬉しかった、楽しかった、安心した、尊敬した自分の気持ちは嘘ではないはずだ。作中の表現に、人の心を月に例えたものがある。月は地球に対して常に表側を見せているが、クレーターの多い不格好な裏側は決して見せない。全ての人に共通する本質が月であるなら、私は美しい光を放つ表側も、穴だらけだがどこか惹きつけられる裏側も、どちらも魅力的で愛しているのだ。
これを以って、私は自分の人間不信に革命を成功させた。「自分の気持ちを信じる」。こんなに穏やかに、それでいてあっという間に変わった私の一側面。この変化に喜びを抱いた私の気持ちを、肯定してあげたい。