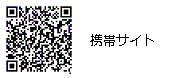食べられる野草で変わった世界
第44回(令和6年度)
全国高校生読書体験記コンクール入選
神蔵美也子さん(新潟県立佐渡中等教育学校)
(取り上げた書名:『早わかり食べられる山野草12か月 見る・摘む・食べる 野山が10倍楽しくなる』/出版社名:主婦と生活社)
私は将来の進路に迷ってました。なぜなら歴史や国語の成績は少し良かったけれどそれを専攻して学びたいと思うほど好きではなかったし、絵を描くのは好きだけど他の人と争ってまでして学びたいと思わなかったからです。
私は今農業が盛んな田舎に住んでいます。だからいつも身の回りには田んぼや畑が沢山あります。最初、引っ越してきたばかりの時は珍しくそれらに興味がありましたが、中学校に上がる頃には見慣れてしまい、興味を失うどころか視野にも入らなくなってしまいました。
その頃出会ったのが『早わかり食べられる山野草12か月 見る・摘む・食べる 野山が10倍楽しくなる』という図鑑です。この本に出会うまで私はその辺に生えている草は決して食べてはいけないと思ってました。だけど、この本に書いてあるのは私がいつも見ていたコンクリートの隙間に生えている草や、砂利に紛れて生えていた草でした。試しに恐る恐る少し食べてみると、売っている野菜と大差ないくらい美味しくて驚きました。それ以来私は、食べられる野草の魅力にすっかり取り憑かれ、植物に関する勉強や仕事をしたいと思うようになりました。
それから私は自分の家の庭を意識して観察してみました。すると、野の草の季節や順番がわかってきました。野の草といえど、冬には全く生えておらず、二月辺りになるとようやくタネツケバナという草が生えてきて、それからオギョウ、フキノトウ、そして五月になれば辺り一面緑になることがわかりました。
農業も同じで五月辺りから準備が本格的に始まります。ただ、やはり手間が掛かるけれど便利なのは農業の方で、冬場も作物を採ることができますし、欲しいものも育てれば気軽に採れます。それにニリンソウとトリカブトのように毒があるものと見分けにくい野草や、食べられるのにアクが強く調理が大変なゼンマイやオカヒジキなどの山菜よりも、人の手で栽培できる植物はとても安全で便利です。それでも私が野草が好きなのは、野草は自分で探す楽しみがあるからです。図鑑と全く同じ野草を見つけた時の感動は栽培する植物ではなかなか味わえません。
私のおすすめの野草はギョウジャニンニクです。野草とは思えないくらい香りが強く、まるでニンニクやニラのように美味しいです。しかし本州では山奥にしか生えておらず、とても繊細なため採りすぎてしまったり雑に扱ったりしてしまうと枯れてしまいます。繊細な野草はギョウジャニンニク以外にも沢山あり、人の手で栽培が出来ない野草もあるそうです。今や私が住む里山の環境までも変わってきているので私が大人になっても同じ野草が採れるのか心配です。実際、農業で使った肥料で土地が汚染されてしまったり、林業に携わる人の数が減り里山が荒れてしまったりしているそうです。だから私は大好きな野草や美しい自然を守るために沢山学び、自然を守れるような仕事に就きたいです。夢を与えてくれたこの図鑑を携えて。