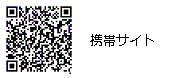『本が導く「戦争のない平和な世界」へ』の二年後
第44回(令和6年度)
全国高校生読書体験記コンクール優良賞
手代木 幸さん(私立東京学館新潟高等学校)
(取り上げた書名:『なぜ戦争をえがくのか 戦争を知らない表現者たちの歴史実践』/著者名:大川史織/出版社名:みずき書林)
令和六年三月九日、私は第26代高校生平和大使として、新潟県長岡市の長岡アジア映画祭の場に立っていました。高校生平和大使というのは「核兵器廃絶と世界平和の実現」の署名活動や平和勉強会や平和集会等の場での意見発表、国連軍縮部に平和スピーチと共に集めた署名を届けている日本の高校生の活動です。この日、小森はるか監督を迎えて「ラジオ下神白」という東日本大震災のドキュメンタリー映画の上映会が行われ、東日本大震災を伝えるイベントで話をして欲しいという依頼と同時に地元新聞社の「東日本大震災‐幼かった私たち‐」という特集記事の取材も受けることになっていました。
私は、東日本大震災がきっかけで福島から新潟に避難しています。福島第一原発事故の放射能による健康被害を心配した両親が、姉と4歳だった私を連れて母子避難を決断し、13年になります。未だに父と離れて生活しています。この話を聞いた時、私はイベントに参加することに前向きではありませんでした。なぜなら、幼かったことで証言といえる記憶はあまり残っていないこと。家族や家を失ったわけでもないため被災者とは言いにくいこと。震災の話題は気持ちが落ち込むためできれば避けたいと考えていたからです。
そんな時、私が手に取った本が「なぜ戦争をえがくのか‐戦争を知らない表現者たちの歴史実践」です。映像表現アーティスト、画家、漫画家など多様なジャンルの10人の表現者の取材記録を紹介した本でした。戦争を知らない表現者たちにとって難しすぎる課題なのではないかと思っていました。しかし、私は読み始めてすぐにこの本を手に取った自分に戸惑いを感じるほどの熱量で戦争をえがいている10人の実践者たちに出会うことになりました。本を読み終わって戦争の惨禍を目の当たりにした人には平和を希求する大きなエネルギーがあるから、心が揺さぶられる被爆証言ができるのだとわかりました。戦争のドキュメンタリー映画監督でもある著者は、取材対象者の映像表現アーティストの小泉明郎さんに表現のモチベーションは何かと逆質問されています。「やっぱり、怒りですか?」という問いへの返答は書かれていませんでしたが、私が聞いた被爆証言者の一人の方のあらわな怒りを思い出しながら、伝えなければというエネルギーの一つに怒りがあることは間違いないと思いました。
漫画家である武田一義さんは、「なぜ戦争という題材に惹かれるのか。」という質問に、二つの見方があり、「たぶんどっちもいたんだという状態を普通に描いている作品を描きたかった。そこにいる人たちに寄り添った作品を描きたい。」と答えています。何となく私には武田さんの言いたいことがわかるような気がしました。私は「黒い雨訴訟」などのニュースを見ていて、被爆した方は誰もが被爆者手帳を欲しいものだと思っていました。しかし、被爆したことを知られたら結婚できない等の理由でひた隠しにした方もいたことを知りました。一つの出来事であっても、人の数だけ思いがあり、選択がある。その選択を大事にしたい、尊重したいということなのだと思いました。
私は、広島で「核兵器廃絶と世界平和の実現」のため被爆証言を聴く機会がありました。戦後79年が経っていることで、被爆証言のできる方が年々減り、戦争や平和を考える上で大きな危機を迎えていました。私は三人の被爆証言を聴き、震える声のなかにすごいパワーを感じました。口に出したくもないと言いながら、それでも伝えようとする言葉を聴いて、その思いを多くの人々に伝えなければと強く感じました。また、広島平和記念資料館の元館長である原田浩さんの被爆証言「原爆症で苦しんでいる人がいる。戦争はまだ終わっていない。」という思いと「家族がいっしょに生活する時間を奪われた。震災はまだ終わっていない。」という私の思い。これらのことから、戦争も震災も被害を受けた人にしかわからないことがあるのではないか。誰かが伝えなければと、私も「震災の記憶を遠ざけない」と決心をしました。三月九日の発言では、「被災体験でも、被爆体験でも一人一人がそれぞれの方法で思いを伝え続け、周囲が受け留め続けていくことがより良い未来をつくる唯一の方法ではないか。」と長岡アジア映画祭の50人の聴衆を前に話をすることができました。
私は本を通して10人の表現者と出会うことで、伝える方法は人それぞれ違ってもいいということ、自分の方法で自分なりに伝えるということが大切なことなのだと教えてもらいました。自分の言葉で自分なりに発言しようという勇気をもらい、大きな一歩を進むことができました。本は私の「戦争のない平和な世界」への扉を開け、「自分の思いを自分なりに伝える」機会を与えてくれました。高校で出会えた本たちと対話でき、感謝します。